基本情報
基本情報
2024年度上期、第171回芥川賞受賞作品の1作。作者は1981年生まれの朝比奈秋。現役の医師です。受賞作となった『サンショウウオの四十九日』は、読めば分かりますが「考える本」で、なかなか難しいことをしようとしています。綺想小説。ただ、ある法則(後述します)をきちんと理解していれば、別に読みにくいことはありません。3時間半で読み終わります。ジャンルは純文学。
私は、この1作だけであれば記事にするつもりはありませんでした。ただ、わけがあります。今回の受賞は同時受賞となり、もう1作は松永K三蔵氏の『バリ山行』という作品です。そしてこの2作があまりに対照的でした。私にはそのことがひどく面白く、それがそのまま記事を書く理由となりました。
何が面白いかって、作品がそうなように、生き方もだいぶ違うことがインタビューで分かりました。作者の朝比奈は小説を読んでこなかったことと、彼には小説に対し希望や熱意のようなものは無かったことが分かります(と、書いてもどこまでも自己申告なので真相は定かではありませんが)。だけどたぶん、才能。天才肌。歳は、なにかのデビューにしては、早い方ではありません。なかなかにいい歳です。ですが、彼が小説を書こうとしてから、実際に書き、恐ろしいことに、初めて賞レースに出した作品はいきなり3次選考まで残ったというのです。これで、彼は自身の才に気がついたと語ります。もちろん、天才たちの中ではよくある話に過ぎませんが、やはりスゴイ。デビュー作がそのまま芥川賞をとったという作家など、いないこともない。直近で言えば市川沙央の『ハンチバック』だし、受賞と同時にその端正なルックスと茶髪で話題となった平野啓一郎の『日蝕』。金原ひとみの『蛇にピアス』などが挙げられます。だが、彼ら、彼女らは多分に小説に触れてきています。そう、その基礎が違います。
でも、朝比奈秋には、そういうバックボーンがありません。
彼は現役の医師で、だからこそ、なのか『サンショウウオの四十九日』の主題は彼の領域の話です。なかなか書けるようなテーマじゃないし、秀逸だと思いました。と、あとはね、外野は黙ってろって話でしょうが、少し私が(勝手な)世論を代弁してみます。彼は「医学部に行って、これは違うなと気づいた」と、コメントしました。「いやいや、何を言っているの?」など、思うでしょう。でもね、彼にとってはやはり違ったのです。お医者様ですが、なにか違うのです。そして、ある転機で小説を書き、ハマる。ふと、書きたいことが溢れている。気がつけば、できることなら、小説を書いて、食べて生きたいと思った。……いいですよね。何者かになりたいと、語る人は、どこかで自身の境遇に満足していない、どこか逃げがあったりします。でもそれって、いわゆる「普通」や「貧困」からの脱出を望む声ですよね。まさか医者が、そんなことは言わない……って、でも、そんなことないのですよ。得てしてすごい作家なんて、もはや、もとよりスゴイ人ばかりです。でも、最近ではそういう人が減っている気がします。とか、ね、もはや作家たらしめるのに、こんな背景を外野が語るのは野暮ですね。

私の地域では、昔オオサンショウウオ刺身で食べてたらしい

美味いとも聞くけどどうなんだろう?
簡単なあらすじ
同じ身体を生きる姉妹、その驚きに満ちた普通の人生。
伯父が亡くなった。誕生後の身体の成長が遅く心配された伯父。その身体の中にはもう1人の胎児が育っていた。それが自分たち姉妹の父。体格も性格も正反対の2人だったが、お互いに心を通い合わせながら生きてきた。その片方が亡くなったという。そこで姉妹は考えた。自分たちの片方が死んだら、もう一方はどうなるのだろう。なにしろ、自分たちは同じ身体を生きているのだから――。朝比奈秋『サンショウウオの四十九日』新潮社 帯より
これは、正確には「あらすじ」ではない。そして大事なテーマについて触れているが、キーワードは欠如している。ですが、あえてだと思います。と、気になるような書きぶりで、プレゼンに近いこの紹介文。私は雑誌で読んだので、単行本に書かれたこの文章を読んだのは、この記事を書くにあたってが初めてでした。でも「あらすじ」は? と言えば、やはり難しい。所謂考える系のジャンルには不要、なのではとさえ思います。でも、ちょっと気になりますよね、この紹介文。「自分たちは同じ身体を生きているのだから――」……なんだこれって。
面白いと思うところ
キーワードは「胎児内胎児」と「結合双生児」。前者は、そこまでだけど、後者のテーマは秀逸だった。簡単に説明すると「結合双生児」とは、1つの身体に、2人の人間(人格)が住まう、というもので、現実にもあることです。例えば下半身は1つだけど、上半身はそれぞれ、もしくは首から上が2つあるという、2つの、2人の人間がくっついて生まれたことを言います。双子が、別々じゃなくて、一部共有して生まれたことです。
私は2回読みましたが2回目の時の方がよく読めましたし、楽しく読めた。それはなぜか、作者は分かりやすく主人公の兄弟、「杏」と「瞬」の違いを書き分けてくれているからです(このルールを知っていた方がずっと読みやすいです)。具体に姉妹は左半身の姉の「杏」、右半身には妹の「瞬」。そして書き分けはシンプルで、姉の「杏」は漢字の「私」を、妹の「瞬」は平仮名の「わたし」を主語としています。
引用します。読んでみて下さい。面白いですよ。これは、妹「瞬」の意識です。
杏はこんなことを考えていて、わたしはただ浴室の鏡に石鹸をつけて泡立て、水滴でぼやけている鏡面をシャワーで洗い流した。水垢のとれた鏡面が浴室と左右非対称の顔を映しだしても、焦点の位置を杏は見ていない。思考し続ける杏をほっておいて、わたしはシャンプーをつけて髪の毛を泡立てはじめた。
鏡にはたった一体の人間が映っている。一体だけど1人ではない。何の因果でかおかしな体に生まれたことに重い息がもれる。双子の姉妹ではあるが伯父と父以上に全てがくっついて生まれ落ちて、そして、今もくっついている結合双生児だから、杏が伯父と父のことを考えてしまうのはしかたがなかった。少なくとも周りにくっついている人間はいないのだから、かつて強く繋がっていた2人の心境が杏は気になる。
わたしは鏡に映るおかしな体を洗っていった。右はなで肩で、左はいかり肩。普通より骨格的にも幅も厚みもある胴体には2人分が詰まっている。小顔矯正どころか、美容外科手術でさえ、どうにもならないレベルで鉢のはった頭の上に泡を立てた。
頭も体も洗い終えても、杏は考え事を続けている。今日はわたしが体を拭いて、頭を乾かすしかないと諦めたところで、杏は手を伸ばして浴槽のカランを捻った。浴槽にお湯が注がれるのを見て、わたしもまた張っていた気が抜けていく。水面が少しずつ上がっていくのを2人で眺めていると溺れていくような心地がした。
もちろん、これは一例ですが、全編に渡って姉「杏」の「私」と妹「瞬」の「わたし」の思考が交差します。この法則をちゃんと理解して、迷子になりさえしなければ、とても楽しく読めます。とにかくすごく挑戦的なことをしています。だって、1人の人間の身体の中に、2人の人間がいるのですよ! こんな小説ありますか!? そうそうないはず、少なくても私は知りません。そして、完璧とまでは言えませんが、その設定をなんとか成立させています。ねえ、気になりませんか? いったい、その場合、そのパターンってどうなるのだろう? と、ワクワク、ドキドキしながら読み進められます。
こういう人にお勧め
かなり哲学な本です。「意識」とは何か? 「人格」たらしめる要素は、なにか。ということを考えさせられます。本作でだいぶ時間をかけて書かれているのは、「自己とは何か」ということについてです。
意識はすべての臓器から独立している。もちろん、脳からも。
これはなかなかにシビレますが、姉「杏」はさらに少しばかり際どい思考に更けます。また引用抜粋しますが、この時、私はいったい何を読んでいるのかとさえ分からなくなりました。
意識はすべての臓器から独立している――。しかし、1つの意識で1つの体を独占している人たちにはそれがわからない。思考は自分で、気持ちも自分、体もその感覚も自分そのものであると勘違いしている。自分の気持ちが一番大切、なんていう言葉を聞くたびにニヤニヤと含み笑いをしてしまう。単生児は自分だけで1つの体、骨、内臓を保有していて思考や気持ちを独占する代わりに、その独占性に意識が制限されている。いや、意識を制限しているのは、この思考や気持ちは自分のものだという傲慢さによるものだ。自分の体は他人のものでは決してないが、同じくらい自分のものでもない。思考や記憶も感情もそうだ。そんなあたりまえのことが、単生児たちには自分の身体でもって体験できないから、わからない。単生児だけでなく、生まれると同時に離れる非結合双生児もそうだろう。とにかく、自分だけのものとして使いこむなり、彼らの意識は脳だったり、心臓だったり、1つの臓器とむすびついてしまうようだ。デカルトの「我思うゆえに我あり」な人たち、つまり脳が、思考が、自らの意識を作り出していると考える医者や科学者たちがどれだけ結合双生児の研究を進めようとも、たどりつく結論は1つで、主観性を省いて客観性のみで証明する科学論文で双生児たち2人の思考が主観と客観を越えて統合されていると証明することになる。そして、自ら論文で証明しておきながら皮肉なことに、誰とも繋がっていない彼らは自分と相手、その主客の統合がなされる感覚を自分では実感できず、ただ自らの主客の分裂に打ちひしがれる。自分も結合双生児として繋がって生まれていれば心底から理解できただろうに、と嘆くことになる……
なかなかにヤバくないですか。この「単生児」というワード、怖いですよね。もはや結合双生児であることの優越感さえ抱いているような感覚……。
意識は脳にない……死は主観的に体験することのできない客観的な事実である……真に恐れているのは意識の死……肉体の死は意識の死とはなんの関係もない……とかとか!
こういうの、好きな人いますよね。そういう方にはもちろんだし、一方で、ちょっと難しいと感じるかもしれませんが、安心して下さい。意外とイケます! というか、イケているような気になります。もちろん全部完璧に理解することなどできませんが、作者が一生懸命トライしようとしていることの片りんは分かります。ある意味、ザ・純文学。という側面があります。面白い、というより、純文学という自由文学に触れることが出来ます。こういうのがクセになる。ハマる、入口になると思いますよ。
ここから読んだ人向けの話
考察(全体的な感想)
まず苦言を……「胎児内胎児」のテーマ(設定)、いりますかね? と、ラストに向けての失速が残念だった。それが、正直な感想です。まず2つの特異な設定が、相乗効果よりも寧ろ相殺している感がありました。たぶん、その設定はなくても満足していたのだと思いました。あのラストの失速ですが、急につまらなくなりましたよね。そして最後の締めくくり。どうも納得がいかない。書ききらなかったのかもしれませんが、やはり残念でした。
このテーマにはちょっと無理がある。もしくは信じられない。ただそれは、言葉が足りないだけであって、実際はそうかもしれない。とは思える。だけど難しいよ。というのが本音です。
感想(両親の愛情)
姉「杏」と妹「瞬」は、声色が違うのでしょうか。それかもっと小さな何かがあるのでしょう。両親は、2人の娘を認めているし、はっきりと違いを認識しています。それは愛ゆえになのだと思うが、この設定はとてもよかったです。ただ、傍から見れば、たぶん無理だろうと思います。はじめに声色と書きましたが、やはりそれは否定します。身体的に、その違いが出せるとは思えません。だからイントネーションの若干の違いなのでしょう。しかし、ほとんど変わらないと思います。でも、それを、当たり前に識別することができる、という設定がよかったです。
意識の共有について
(発見が)5年遅れの「瞬」は、本当に存在しているのか?≒「二重人格説」。
このことは、戸籍を与えたことと、肉体的な特徴・差異(右半身と左半身)をわざわざ記述していることで、あたかも2人は別の人間であることを説明することは出来ますが、いかんせん、それほど簡単な問題ではないと思います。要は、たしかに肉体は2つあった。だが、それイコール「心」(≒「意識」)は果たして別々なのか? ということです。ここの書きぶりは曖昧ですし、かつ、作中に「二重人格」とも記載があります。これは内省のうちに辿り着いた、ひとつの可能性ということが分かりますが、私は「二重人格」の方が現実味を帯びていると思います。
そうして、やっとひとつ帰結する。「胎児内胎児」です。私はこの設定は不要ではないのかと言及しましたが、やはり必要なリードだったのです。これは、「胎児内胎児」がリアルだから、当然、姉妹も別々としなくてはいけないと決めたのです。誰が? そう、周りですよ。だから先に「胎児内胎児」を語り、そして5年のラグがあるのです。その時間は、「杏」にとって必要な時間だったのでしょう。
という、この作品に触発されて、私もかなり挑戦的な考察をしてみて、〆ることにします。輪郭くらいは見えてきましたでしょうか?
皆さんはどう思いましたか?
最後に、基本情報で記載しました第171回芥川賞を同時受賞した『バリ山行』についても記事を書いていますので読んでいただけたら幸いです。
ホワイトデーのお返し決めた?
今年こそセンス良く買ってみませんか?
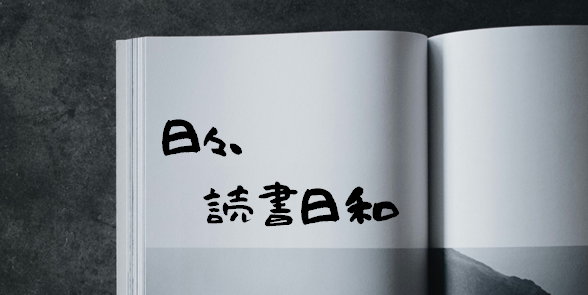










コメント