基本情報
2024年度下期、第172回芥川賞受賞作品の1作。作者は2001年生まれの鈴木結生(ゆうい)。2024年『人にはどれほどの本がいるか』で林芙美子文学賞佳作を受賞してデビュー。そして次作、翌年には本作『ゲーテはすべてを言った』で芥川賞を受賞します。前の記事の『DTOPIA』でも、ホセすごい、経歴ヤバイ、とかそんなことを書きましたが、鈴木結生も早い! ビックリしちゃいますよね。気がつけば、芥川賞作家になっていた。周りも、本人でさえ思うかもしれません。……こんなことを書けば、僻みかもしれませんが、私は彼の、彼らの才能が憎い。でもすぐ訂正。『ゲーテはすべてを言った』は良かった。面白かった。そして何より、私には、書けない。読めば分かりますが、この一作を書き上げるまでの背景を想像すると、先の才能が云々と言う言葉は間違っている。まだ若いながらも、積み上げた歴史が伺えるからです。ただ、若いだけで、キャリアは抜群だってことが、受賞者インタビューでもよくわかりました(ここは省略します)。
さて、ここで少し余談。私は先の「林芙美子文学賞」がなんなのかよく知りませんでした。どこかで聞いたことがあったような、というくらい。調べてみました。林芙美子文学賞:北九州市が主催、朝日新聞出版が協力しているもので、2014年に設立された文学賞。中・短編作品を対象にしているもの、名前の由来は北九州市とのゆかりの深い作家「林芙美子」からとったそうです。ちなみにこれは、「森鴎外」にちなんで創設された北九州市自分史文学賞を継承・発展させたものだそうです。
知らなかった……だけどやっぱりどこかで聞いたことがある。そう! このサイトでも書きました『サンショウウオの四十九日』の朝比奈秋もここの出身でしたね。で、彼は大賞とのこと。どうりで、というかすごい。キテる! 林芙美子文学賞! ということは2期連続で芥川賞を受賞した文学賞ということですね。すごい。
また、鈴木結生、受賞時23歳。若い! すごいですね。そして書くもの、圧倒的知識。読み始めればすぐに分かります。本作は全編ゲーテを巡る書誌学的ペダントリーで押し、その過剰さで読者を捩じ伏せます!……すいません。「ペダントリー」こんな言葉、知りませんよね? 当然、私もこの横文字について、ググりましたww 「ペダントリー」この言葉は選評である先生が使っていました。それを抜粋、それですぐに私も意気揚々と使ってみた。という感じなのですが、それも全部白状する私です。気になった方は、ぜひ調べてみて下さいww
さて、基本情報に戻って、読了時間目安は4時間、純文学。ちなみに、これを読み終わってから、いよいよと思いまして、ずっと逃げてきたゲーテの代表作『ファウスト』も読みました。1はいい、4時間だし、面白いと思った。が、問題は2です。8時間もかかったこと、そして、私にはまだ早かった。正直分からない。もっと詳しい歴史背景とか知っていないと、いろいろ厳しいと思ったのが正直な感想です。ですが、読んで、言ってやりましょうよ。「世の中には2種類の人間しかいない。『ファウスト』を読んだ人間と、読んでいない人間だ!」的な、余談も過ぎる。それと、同時受賞となった安堂ホセの『DTOPIA』の記事も書いています、こちらも読んでくれると嬉しい。
簡単なあらすじ
ゲーテ学者が侵した、
超えてはならなかったはずの一線――。ゲーテは言った。確かに言った。
高名なゲーテ学者・博場統一は一家団欒のディナーで、
彼の知らないゲーテの名言と出会う。
ティー・バッグのタグに書かれたその言葉を求めて、
膨大な原典を読み漁り、長年の研究生活の記憶を巡るが――。
ひとつの言葉を巡る統一の旅は、
創作とは何かという深遠な問いを投げかけながら、
読者を思いがけない明るみへ誘う。
若き才能が描くアカデミック冒険譚!鈴木結生『ゲーテはすべてを言った』朝日新聞出版 帯より
いい紹介! なんというか、純文学っぽくない感じがしますよね。そうですね、ゲーテの名言の出典を追いかける文学ミステリー、こんな感じでしょうか。

ゲーテさんの名前は知ってるけど何した人かね。

ドイツの詩人、劇作家、小説家、自然科学者など。昔の人のマルチな才能すごい。
面白いと思うところ
ここで、これを引用することが正しいのかは分かりませんが、今爆ヒット中の映画『国宝』の原作者、吉田修一が選評で、ずいぶんと長い文章を書いています。これがなかなか読んでいて気持ちがいいことと、愛を感じたので、ここに引用することにしました。また、選評では総じて本作『ゲーテはすべてを言った』に対する各先生方の評価は高いように感じられました、補足までに。さて、それでは下記に吉田修一の選評を全文引用します。
「ゲーテはすべてを言った」小説から書物の匂いがした。もう何年も小説の選考にたずさわっていながら、久しく嗅ぐことのない匂いだった。この匂いはさらに様々な記憶を蘇らせた。臆面もなく書けば、真冬の学生服の冷たさ、図書館の少し浮いた床板、なんとなく棚から引き抜いた詩集。『僕の青春は悲惨な嵐に終始した、時たま明るい日ざしも見たが』もちろん意味など分からない。文学とは無縁だった地方の少年には、正直、縦から読んでも横から読んでも、なんのこっちゃでしかなかった。ただ、なんのこっちゃでしかなかったのだが、そこに書いてあるなんのこっちゃが、これまで自分が知らなかったなんのこっちゃであり、その新しいなんのこっちゃに今自分が触れたのだということだけはちゃんと分かった。
今回、まだ20歳そこそこの若い作者が書いたこの古色蒼然とした小説に、なぜかとても好感を持った。その理由はなんだろうかと考えてみれば、ここには喜びが書かれているからだと気づく。何かを知ること、知りたいと欲すること、人間が持つそんな根源的な喜びがこの小説には満ちている。そしてこの若い作者が持つもう1つの美点は、その鷹揚さにあると思われる。小説が窮屈ではないのだ。たとえば作中にこんな文章がある。“自分自身がゲーテになっているところを夢見た。職人気質で勤勉な父と芸術家肌で快活な母の子供で、立派な家があって、何事にも泰然自若とし、美しい女と恋をし、賢い友と哲学を論じ、詩を作る”夢の話ではあるが、まさにこの小説の世界観そのものであり、選考会で出た無自覚なコンサバティブという鋭い指摘には肯首しつつも、まだ若い作者にはしばらくの間はこのまま自分の文学世界を広げてほしいと願う。遅かれ早かれファムファタールは現れ、賢くない友に悩まされる時は来るのだから。吉田修一
いいですね。ですが、後半の「コンサバティブ」とか「ファムファタール」など、いったいどうしてこんな言葉選びをするのでしょうね……とか、そんな文句を言うことは止めておきましょう。また本作にはユーモアもあります。きっとあなたも明日から使えるジョークをひとつ紹介します。
「ドイツ人はね」とヨハンは言った。「名言を引用するとき、それが誰の言った言葉か分からなかったり、実は自分が思い付いたと分かっている時でも、とりあえず『ゲーテ曰く』と付け加えておくんだ。何故なら、『ゲーテはすべてを言った』から」
うーん、まあ、まあって感じでしょうか。それにしてもゲーテの言葉になると、どんな人もやりたい放題。たとえば私の大好きな作家、村上春樹も悪用? しています。彼は、小説の登場人物に『ゲーテが言っているように、世界の万物はメタファーだ』と言わせているが、これはかなりの超訳ですww
こういう人にお勧め
きっと読み返す本になります。現に私も、短い期間で3回読みました。どんどん好きになる。ありていに言ってしまえば、1回目はよく理解できないかもしれません。でも、ハッとします。なぜなら、構成がとてもよくできているからです。純文学とは、ストーリーがなくても、それが許される分野です。でも本作にはちゃんとあります。全部つながっています。そして読み返してみると気がつきます。1回目より楽しいって! 1回目は~のところと矛盾するようですが、読みやすい。そうですね、ミステリーなんだ。ちょっと? いや、かなり鼻につくぐらいの言葉選びとアカハラがありますが、それも、結局はこの構成と、面白さがカバーします。
それと、ゲーテが好きな人、言語・文学が好きな人、学者さんにはもちろんオススメです。紹介してあげて下さい。そして何より下記のフレーズです。これは、このブログでも英語記事を多く書いていますが、ここで紹介しないわけにはいかない。是非是非!
Love does not confuse everything, but mixes
このワードが本作のキーワード。さあ、あなたなら、どう訳しましょう。
→「愛はすべてを混乱させることなく、混ぜ合わせる」……こんな感じでしょうか?
いやいや、翻訳家の話ではありませんが、これを下記のように訳せばグッと締まります。
→「愛はすべてを混淆せず、渾然となす」
混淆(こんこう):異種のものが入り混じること。そういうものを入り混じらせること。
渾然(こんぜん):別々のものが一つにとけあって、差別のないさま。
※上記の四文字熟語として「玉石混淆」「渾然一体」などが挙げられます。
そして本作は、この言葉の、出典を巡るミステリーなのです。果たしてこの言葉は、本当にゲーテの言葉のでしょうか……どうでしょう? 楽しそうじゃないですか♪
また、他にもまだまだあります。本作には、物書きの心情がね、よく書けているのです。たとえばこんなところです。
何篇自分の文章に目を通しても、言葉がてんでバラバラに感じられて仕方がなかった。なるほど多くの単語があり、それぞれに役割があって並べられている。一つ文字を他のところと取り替えたら、途端に全体の意味が通じなくなるだろう。しかし、だからといって、それら一つ一つの語彙が完全に必然性を持ってそこにあるとは、統一にはどうにも信じられなかった。具体的には、「物語の序盤」は「話の冒頭」でもいいし、「あらゆる学問」は「諸学」でもいいだろう、「言います」なんて「語っています」でも「こう独白します」でも何でもいい、大体最後の思想史めいた部分について自分は本当に熟慮したのか?……とこう考え始めたら全くキリがなかった。何より恐ろしいのは、これを書いていた数ヶ月前の自分はその必然性を確信していたということである。しかし、現時点の彼が信頼できるものは結局のところ、その数ヶ月前の自分だけなのも確かで、彼がよしとしたからには自分もよしと思えるだろう、と我慢して先を読み続ける。
鈴木結生『ゲーテはすべてを言った』より
最終の見直しでは、一つ一つの語彙に気取られるのではなく、パラパラ捲っていって、リズムに狂いがないか、それだけを点検する。全体を俯瞰すれば、読み物としてそこまで悪くないようにも思えたが、余りに欲張りが過ぎて、必要以上に多くのことを盛り込んでしまった感もまた否めなかった。
鈴木結生『ゲーテはすべてを言った』より
こういうのがね、私をくすぐるのです。……もしかしたら私は、ちょっと贔屓しているのかもしれません。でも、物書きなら、きっと好きだと思います。
ここから読んだ人向けの話
済補について
きっとあなたもどうしたって引っかかったはずです! なんですかこの書き方!? 本作では、スマートフォンを「済補」と書きます。作者(鈴木)の意図ですか? もちろん、それはそうでしょうが、考えてみて下さい。これは、綴喜が書いています。統一の話を聞いて、それを小説にしています。誰のチェックを受けて、それか、はじめからそう言われていたのでしょう。統一の強いこだわりで、たしかに統一はネットからの情報には懐疑的でした。本、紙媒体を、いや紙媒体だけに信頼をしている節さえあります。これね、分からないこともないですよ。書き換え可能な電子データではなく、紙。
じゃあ、「済補」とは、いったいどのような意味でしょうか?
これは、ただの外部記憶装置にしか過ぎない。たぶん、昔のガラケーならば、統一も「携帯」とだけ書くことを許したでしょう。ですが、現代のスマホは、ネットへの接続をメインに使います。様々な情報へのアクセスは簡単です。便利反面、問われるリテラシー・信憑性、だから、統一はそうは使わない。単なるメモ。済んだことを、補う。ま、にしても毛嫌いが過ぎますような気もします。これは、皮肉。それか、何か私たちに警鐘を鳴らしているのかもしれません。
統一の夢の話と、彼の罪について
3人の男たちが出てきて、その後に一際眼光の鋭い男が続いた。
彼は自分の本について唾を飛ばしていた。鈴木結生『ゲーテはすべてを言った』より
まず、この彼は「先生」ではないですよね。この、眼光鋭い男こそが、唾を吐いた「彼」なのでしょう。分からなかった。でも、私はこれを「卑下」だと思いました。ここは、夢の中。そこで、無意識にそういう一面を暗示している。村上春樹風に言えば、ひとつのメタファー。どうだろうか? 苦しいのは私が一番分かっていますが、それでも何かしらの解が欲しい。そのくらいの違和感がありました。それか、これは作者が、本作に対して、そういう一面があることを分かっていて、その先手を打っているだけなのかもしれない。いかがでしょうか。
次は、罪の話。
統一は、出典の確認がとれていないにも関わらず、ゲーテのだ……もはやそうであって欲しいと願い、あたかもそれが本物であるかのように、「彼もこう言いました」と発言する、という一つの罪を犯しました。……分かりますよ。でも、そこまでの大罪でしょうか? 気持ちよくなってしまった。ただの言い間違え、筆が走った、に近い感覚……いや、そこじゃない。私は、このことよりも、むしろ統一が夢の中で「先生」にそれを言わせたことの方が、大罪なのだと思いましたね。希望的観測。そうであって欲しい。この悪魔の証明のようなことからの、逃げ。その思いが強過ぎた結果。これは、このことの方が、学者として大罪なのだと思いました。
然紀典の行動について
面白かったですよね! 繰り返すようで恐縮ですが、実によくできていると思いました。結局は、架空の自作を、あたかも本物の図書のようにし、そこから引用した、という、捏造。ちょっと自分でも書いていてよく分からないですがww
そしてそれを、自身でカミングアウト。しかも「惟神光」という偽名でもって。はじめは混乱。でもここではっきりと、「惟神光」とは「然紀典」その人である、ということが明かされています。
そしてシビレルことを言う。
「私は学問を破壊したいのでもなければ、告発したいのでもなく、むしろ容認したいのです。私は学問というのは失敗と間違いの連続である、と思う。失敗と間違いこそ、多様性の根幹にあるものだと思う。神話や言語の多様性は、失敗と間違いです。しかし、この時代に間違えることは難しい。だから、私が盛大に失敗してあげました。失敗している最中は、確かに仲間に対して申し訳なかった。けれど、彼らは分かってくれます。私は私が『神話力』で書いた力を実行したに過ぎません」
鈴木結生『ゲーテはすべてを言った』より
待って下さい!
これ、既視感があった。でも、すぐには気がつかなかった。再読し、そうだ、これ統一の夢で、「先生」が話していたことじゃなかっただろうか……
世の中は、いつも同じものだね。いろんな状態がいつも繰り返されている。どの民族だって、ほかの民族と同じように、生き、愛し、感じている。あらゆることは既に言われていて、われわれはせいぜい、それを別の形式や表現で繰り返すだけだ。
鈴木結生『ゲーテはすべてを言った』より
すべてはつながっている。……それで、本当のところは? もう、私はそこまで書きません。
最後に、端書きからはじまる本作ですが、その中でこの小説を補填することに、統一自身が既に発表している「未発表のゲーテ書簡について」も併せて読まれることを強く勧める。と書いて、リンクを貼っています。私はいわゆるこういうカラクリらしいものは、気にせず読み飛ばすようにしているのですが、この記事を書くにあたり一応確認しておくかと思い、下記のリンクを覗いてみました。そしたらまさか、鈴木もやっていましたww 2027年1月ww
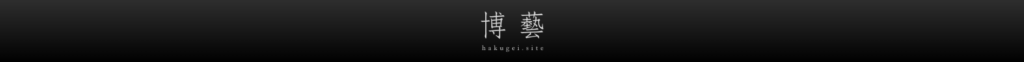
よかったら飛んでみて下さい。とは言ったところ、もう皆さんは試してみたでしょうか。すごいですよね、やったら面白いと思っても、なかなかここまではできない。
皆さんはどう思いましたか?
バレンタインまであと少し!
今年の流行品をプレゼントしてみませんか?
1. GODIVA チョコレート詰め合わせ4種類52個入り
2. 銀座千疋屋 銀座フルーツクーヘン8個入り
3. ヴェリスタ極上辛口スパークリングワイン6本セット
4. NILE 香水 サボンカシミア オードトワレ50mL
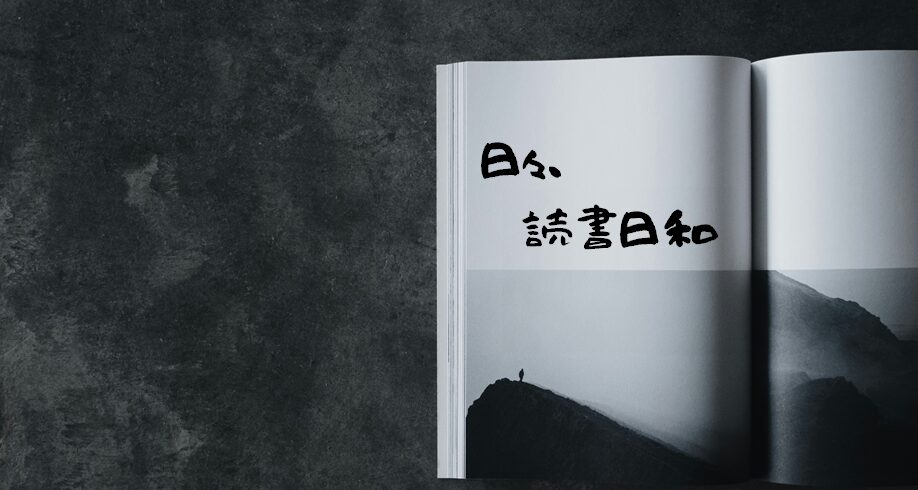
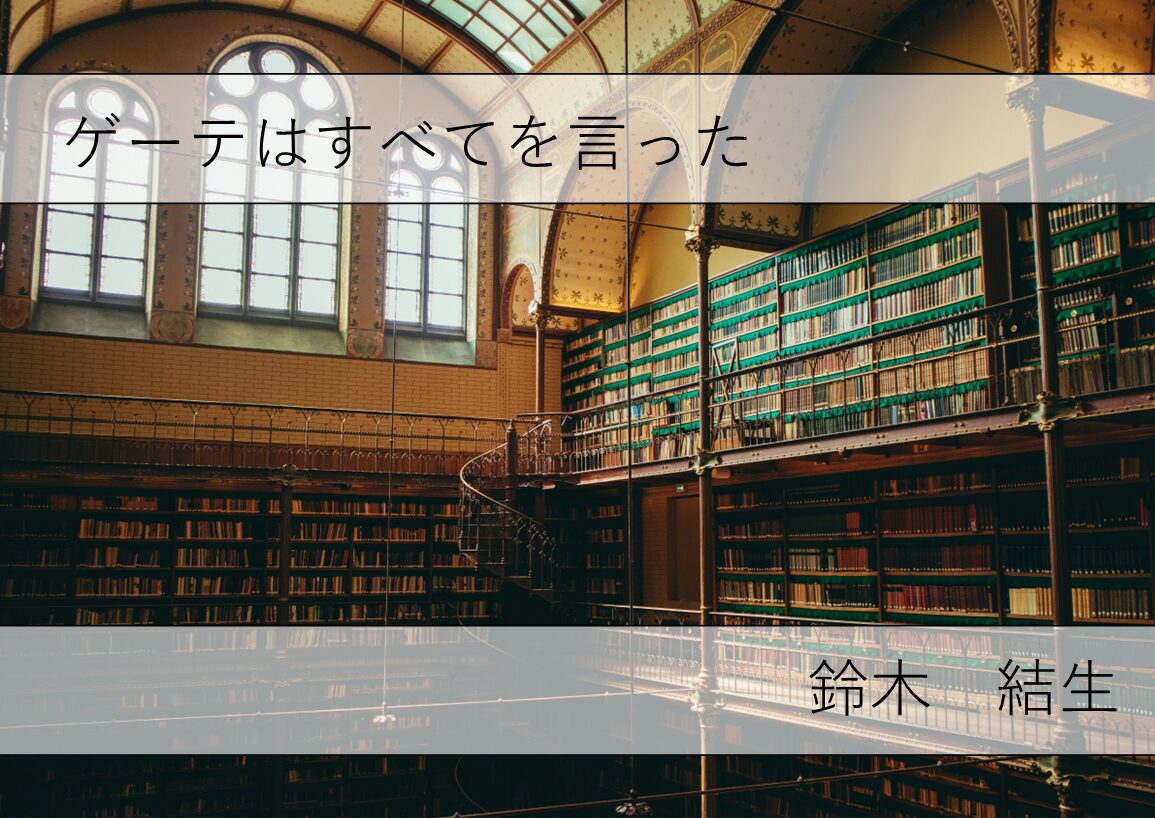









コメント