基本情報
基本情報
本作品の作者、阿部公房は前衛作家で、まぎれもなく天才です。脳みそが違う。この前書店に行った際に、生誕100年ということで特集が組まれていました。『箱男』が永瀬正敏主演で映画化するということでも再び注目を浴びていますね。今回紹介する『砂の女』は1962 年の作品です。ジャンルは純文学で、読了目安時間は6時間。阿部公房と言えば、先に挙げた2作品も代表作ですが、『壁』で芥川賞を獲っています。また、彼は東大医学部を卒業していますが、医者には初めからなる気は無かったそうです。ほんと、この年代の作家で、同学で親交の深かった大江健三郎といい、三島由紀夫といい、すごいですよね。
さて、今回の主役「阿部公房」はたいへん独創的で、とくに本作など、寓話感もあります。そして、なにより一番はカフカの『城』が浮かびます。
って、ちょっとこれじゃあ分からないと言う話かもしれませんが、要は、ちょっと難しいです。というか、世界観に、脳みそがやられそうです。私はこれまでに6回読んだことが過去の記録からも分かったのですが、はっきり言えば、まだ、足りない。これは、理解ができないとか、そういうことではなくて、奥行きがあります。それと、解説で書いてあったことが、ピンときました。『砂の女』は、優れた芸術作品で、神話的な広がりもあるということです。たしかにそうだ。いち小説という枠の中では収まりきらないほどのパワーを秘めています。
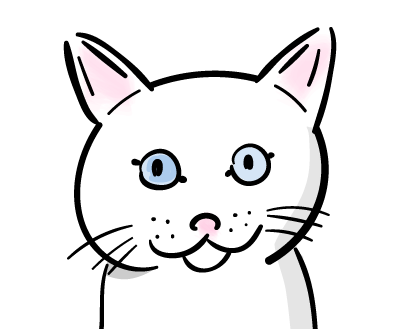
噛めば噛むほど味が出る。まるでスルメ。

そもそもこんな設定を思い浮かばないよね。
簡単なあらすじ
砂丘へ昆虫採取に出かけた男が、砂穴の底に埋もれていく一軒家に閉じ込められる。考えつく限りの方法で脱出を試みる男。家を守るために、男を穴の中にひきとめておこうとする女。そして、穴の上から男の逃亡を妨害し、2 人の生活を眺める部落の人々。ドキュメンタルな手法、サスペンスあふれる展開のなかに人間の存在の象徴的姿を追究した書下ろし長編。20 数ヶ国語に翻訳された名作。
阿部公房『砂の女』新潮文庫 裏表紙より
引用ですが、確かに表面を掬えばその通りですが、この小説の面白いところを紹介できていない引用だと、私は思います。なんというか、迷い込んだ森、蟻地獄に嵌った、タイムトラベルした、など、正直その背景は何でもいいのですが、とにかく日常(常識)から切り離されたところに、男が 1 人。そしてそこに女がいた。男がこれまでに生きた人生に、その価値観や常識は一切通用しない。知らない世界がある。男は、そこで何を感じ、何を体験するのかを、描いた傑作です。
面白いと思うところ
唯一無二の非日常感! これまでの常識を疑います。また、要所に張り巡らされた名言。いや、もしくは迷言。たとえば私の一番好きなフレーズはこれです↓
欠けて困るものなど、何一つありはしない。
幻の煉瓦を隙間だらけにつみあげた、幻の塔だ。もっとも、欠けて困るようなものばかりだったら、現実は、うっかり手もふれられない、あぶなっかしいガラス細工になってしまう……要するに、日常とは、そんなものなのだ……だから誰もが、無意味を承知で、わが家にコンパスの中心をすえるのである。
阿部公房『砂の女』新潮文庫p103
後半はともかく、この、前半のフレーズです。ネタバレになってしまうので、どのような局面で書かれたかをここでは書きません。ですが、なかなか痺れましたね。
それと、世界観の説明に簡単なポンチ絵を挿絵にさせて頂きます。また舞台がね、すごいんです。砂・砂・砂、聳える砂の壁。海・傾斜、縄梯子……こんなです↓
-1-1024x573.png)
-1024x576.png)
-1024x572.png)
また、砂漠とまでは言いませんが当然渇いています。なぜなら周りは砂・砂・砂、そんな局面では「水」は命を繋ぐ大切な鉱物です(←鉱物と書きましたが、本作ではこういう表現がされています)。そしてこんな名言があります。
思考も、判断も、渇きの前では、熱にほてった額に降った雪の一とひらにしかすぎなかった。十杯の水が飴なら、一杯の水はむしろ鞭にひとしい。
阿部公房『砂の女』新潮文庫p172
どうですか、これ。リアルなんですよね! 没入感、世界に、潜ると、そうなんだよな! と、まるで声を出してしまうくらいに、悔しいくらいにハマる言葉を投げかけてくれます。
本作には人間の本質のようなものが、見え隠れしています。主人公が正直だからです。脱出を試みる画策のなかに、腹黒い一面がありますが、阿部公房は、それをあえて隠さない。置かれた状況への不平不満を嘆き、吐露します。
よく、感情移入がどうだとか聞きますが、はっきり言えば、私はそのような感情をほとんど体験しません。でも、『砂の女』にはありました。ということもあれば、俯瞰して、まるで見世物小屋でも覗いているような気分にもなります。「ああ、可哀そうに」なんて感情をあてていた自分もいたりして、驚きます。唯一無二の非日常感! これまでの常識を疑います。そしてそれを可能にするのが、阿部公房の非常に写実的な表現なのです。
こういう人にお勧め
個人的ですが、小説冒頭に書かれたメッセージとしては、J・D サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』の「母に捧ぐ」が最も有名だと思っていますが、『砂の女』にもあります。
―罰がなければ、逃げるたのしみもない―
これは引きつけられる。そしてどこか、マゾ心をくすぐりそうですねww 『砂の女』は、暗い作品ではありませんが、たとえば人間の本質が伺えるような怖さがあります。心を覗きます、真理の探究があります。
ここから読んだ人向けの話
考察(生き方について)
「しかし、これじゃあまるで、砂掻きをするためにだけ生きているようなものじゃないか!」
阿部公房『砂の女』新潮文庫p46
寓話ですよね。優れた芸術作品に対して、語るのは野暮かもしれませんが、『不思議の国のアリス』みたいでした。愛郷精神が行き届いていますから。なんて一言で済まされてしまいますが、ようは彼らにとって、村を守っていくことは当たり前のことで先祖代々から受け継がれてきた精神ってことでしょうか。きっと何十年、何百年も前から同じように生活してきたのでしょう。砂はあって当たり前のもので、今の生活を不便と疑ってもいけない。なにか宗教的なものさえ感じます。日本古来の八百万の神の精神ではありませんが、砂は彼らにとって神様と等しいようなもの(寄り添うべきもの)なのかもしれません。
『不思議の国のアリス』で言う木の根っこの穴に落ちた先、『千と千尋の神隠し』で言うトンネルを抜けた先、本作で言う松林を抜けた先からは、自分の常識が通用しないそんな世界が待っている。そんな始まり方を感じました。
あいつについて
本作において、傍点をつけてまでの強調の心が何であるのかの考えてみます。あいつ=妻なのですが、ひとつに当て付け、そしてほんとうは大好きだったのだと思います、でも、どうにも上手くいかなかった。どこかで自分は不適合者だと自覚します。しかし、忘れたくなかったし、忘れてほしくもなかった。愛し合っていた……はず。だけど、男もそうなように、妻も、生きるのが下手くそだったのです。私はこれを、ひとつのラブレターでもあると思っています。偏執的かもしれませんが、阿部公房の私小説のひとつで、メッセージかもしれません。不器用な作者は、この全編に張り巡らせた不思議な世界を隠れ蓑にして、伝えたかった。別れたか、もしくはそのもっと前、ただ、フラれただけなのかもしれません。それを、詩にしたに過ぎないのかもしれません。というのが、私の考えです。ひねくれた考えかもしれません。そもそも、本作がいったい何のメタファーなのか、とかそういうことを議論することは、きっと不毛。掬い上げてみると、指の間をサラサラとすり抜けていきます。砂。シンプルに冒頭の基本情報に帰結します。なぜなら『砂の女』は優れた芸術作品だからです。
皆さんはどう思いましたか?
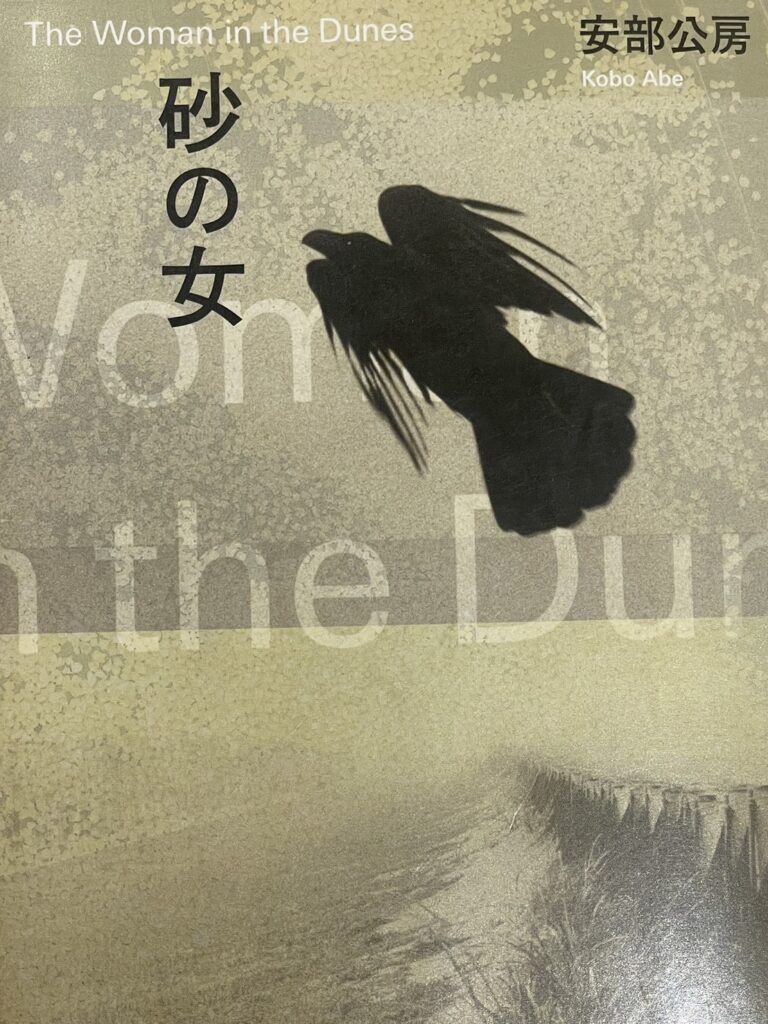
今!売れている電子機器5選!!💻
Amazonデバイス機器で今、最も売れている商品です!!
1. 【整備済み品】Apple iPhone SE(第3世代) 64GB スターライト SIMフリー
コンパクトでも高性能。A15 Bionicチップ搭載でサクサク快適。SIMフリーだから乗り換えもスムーズ。
2. 【整備済み品】ノートPC LIFEBOOK A576 /15.6型/Celeron/Win11 Pro/MS Office付き
仕事や学習に最適。大画面15.6型で作業しやすく、Office搭載ですぐに使える便利な1台。
3. 【整備済み品】Apple iPad(第9世代) Wi-Fi 64GB スペースグレイ
動画視聴や読書、学習にもぴったり。高性能チップでスムーズに動く、人気のiPad。
4. Amazon Fire TV Stick HD
テレビに挿すだけで動画配信サービスを大画面で楽しめる。リモコン操作も簡単で快適なストリーミング体験。
5. Amazon Fire HD 10 タブレット(32GB ブラック)
10インチの大画面で映画やマンガも迫力満点。コスパ抜群のエンタメ用タブレット。
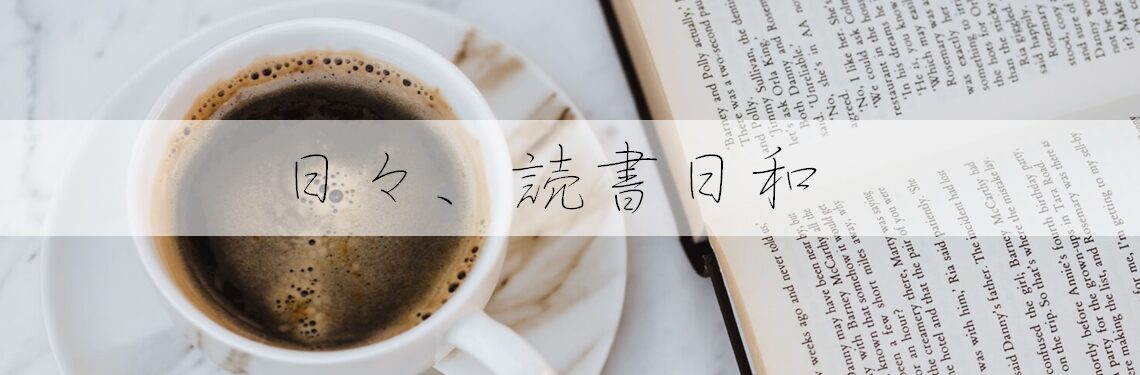
.jpg)






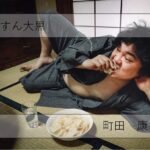

コメント